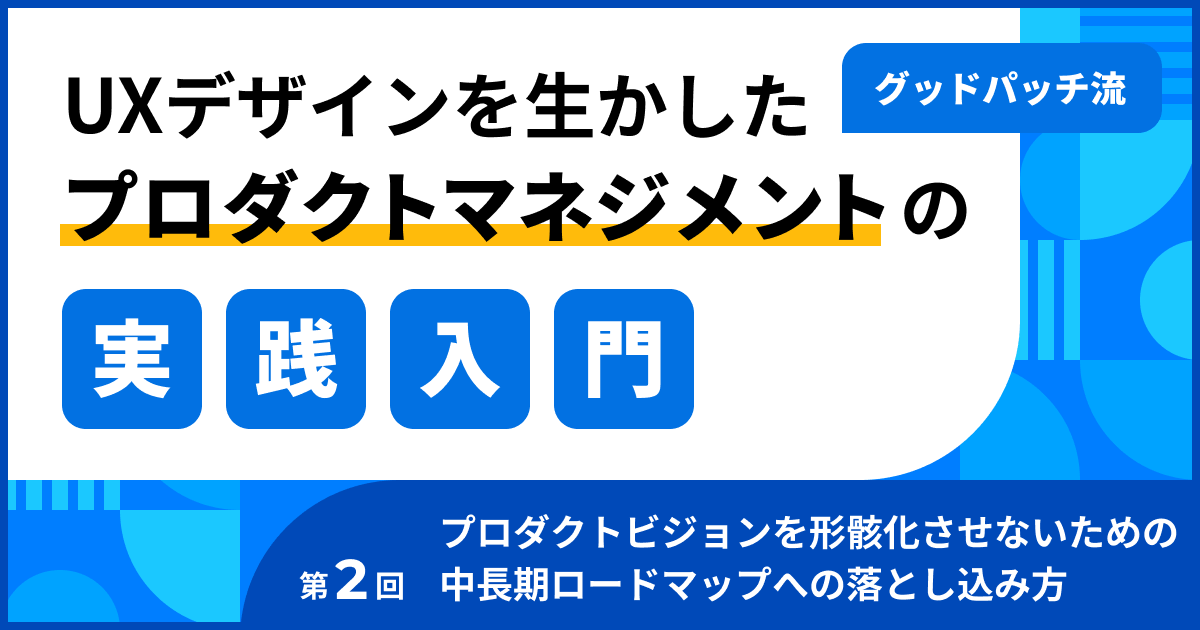はじめに
前回の記事では、プロダクトビジョンの役割や設計プロセスについて紹介しました。しかし、プロダクトビジョンを立てたものの、形骸化してしまい、うまく活用できていないというケースをよく耳にします。プロダクトビジョンという目的地が遠すぎて、どう向かっていけばいいのかチームで共通認識が取れていないためです。
このようなケースでは、プロダクトビジョンに向かう道筋を示した「中長期ロードマップ」の策定が有効です。本記事では、プロダクトビジョンを達成するためのステップを示した中長期ロードマップの設計手順の例を紹介します。3~5年程度の中長期的なロードマップを策定する際に、ぜひ参考にしてみてください。
中長期プロダクトロードマップの意義
中長期ロードマップを策定することにどのようなメリットがあるのか。基本的には前回の記事内のプロダクトビジョンの意義で紹介した、以下の3点を補強するような形になります。
1.プロダクトマネージャーの意思決定の判断基準に使うことができ、メンバーの納得度を高める
判断軸がプロダクトビジョンのみでは抽象度が高く、プロダクト開発のさまざまなフェーズにおいてすべての意思決定に用いることは難しいです。ロードマップがあることで「今はこのタスクにリソースをかけるべき」といったように、時期や状況に応じて企画の優先度を決められます。このようにして判断された優先度であれば、メンバーもフォーカスすべきタスクに納得度高く取り組めます。
2.企画やKPIを立てやすくする
プロダクトビジョンを達成するための企画やKPIは、一段ブレイクダウンしたステップがあると、さらに考えやすくなります。
例えば「ストレスなくオンラインでもコミュニケーションできるようにする」というプロダクトビジョンをかみ砕いて「思い立った時に会話を始められる」というマイルストーンをおくと、どうでしょう。「会話を始めたい相手にメッセージを送る」という企画や「会話が行われた回数」というKPIが浮かんでくるのではないでしょうか。ロードマップ上のマイルストーンを意識することで、具体的な策や指標が立てやすくなり、その結果プロダクトビジョンの達成に近づきます。
3.メンバーのモチベーションにつながる
プロダクトビジョンは、基本的にすぐには達成できない遠い目標を設定します。そのため、どのようにプロダクトビジョンを実現するのかが示されていないと、だんだんとメンバーのモチベーションが下がってしまうこともあります。中長期ロードマップがあることで、プロダクトビジョンを達成するための道筋が見え、メンバーそれぞれがより自分ごととして取り組む手助けにもなります。
以上のように、中長期ロードマップを策定することで、プロダクトビジョンを策定する意義を強めることができます。今回は、プロダクトビジョンを起点にして中長期ロードマップを策定するワークを紹介します。プロダクトビジョンを活用しながら、よりチームの目線をそろえたい時に活用してください。