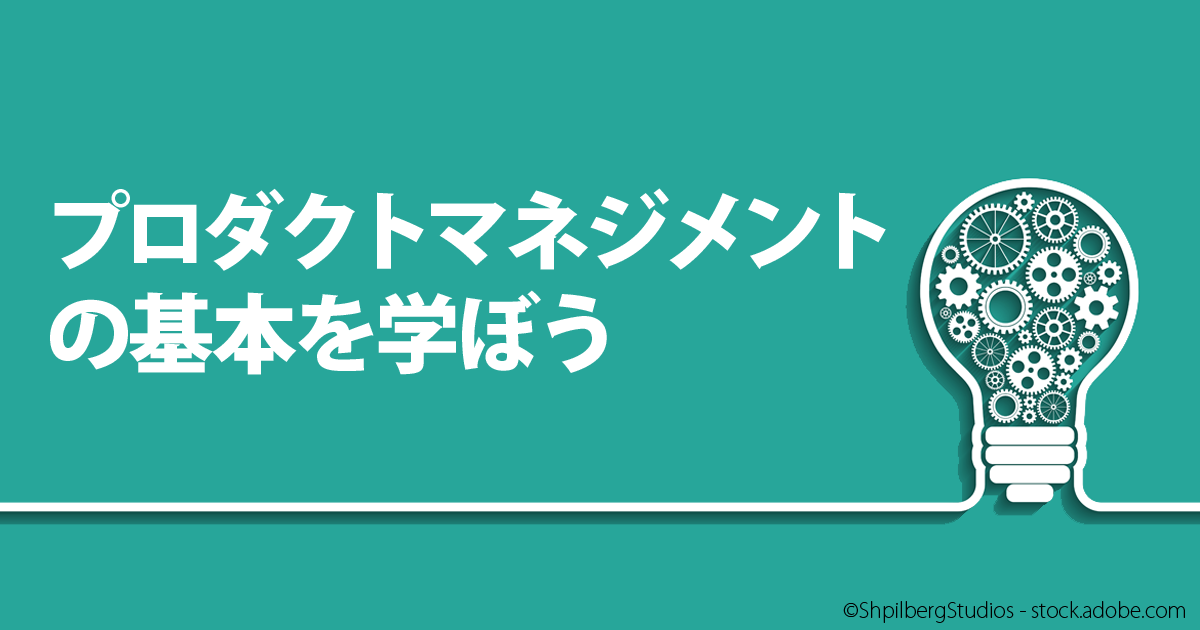施策の成果を計測する
プロダクトとKPI
プロダクトを無事リリースするにあたり、そのプロダクトがどのようにユーザーに受け入れられたかを計測できなければ、当初設定したゴールに対して成功だったのか失敗だったのかがわからない。
そこでプロダクトマネージャーとしてどんな指標を参照するかはプロダクトの成功を定義する上でとても重要な判断である。この指標こそKPI(Key Performance Indicator)だ。KPIを正しく使うためには、まずKPIとはどんなものかについて正確な理解が必要だ。簡単にまとめると以下のようになる。
| KPIたらしめるもの | KPIにはならないもの |
|---|---|
|
数字
(5%、10億円、200万人)
|
言葉 (最高品質、即日配送、地域No.1) |
|
比較可能 (前年比、地域別、プロダクト別) |
単独の値
(100、500個、3000人)
|
|
時系列データ (過去3年、直近18カ月) |
ランダムデータ (非連続データ) |
|
自社で取得可能 (ソースが自社データ) |
外部ソース依存 (マーケティングリサーチ、メディア) |
|
社内で共通理解があり、行動可能 (何のためのデータか) |
自己満足で終わっている (大きい数字で見栄えをよく) |
また数字を使ったからといってすぐにそれがKPIとして機能するかというとそうでもない。そこでよいKPIであるための5つのチェック項目がある。それが”SMART”ルールだ。
- S:Specific(具体的に表現されている)
- M:Measurable(数値計測が可能である)
- A:Agreeable(ステークホルダー間で同意できる)※
- R:Relevant(目標に関連している)
-
T:Time-bound(期限が決められている)
※AをAchievable(達成可能)とする場合もある
またスタートアップにおいて特にPMF(Product Market Fit)を超えて成長ステージに入ったプロダクトに関しては、成長を示すKPIを選ぶことがほとんどだ。ベンチャーキャピタルに対して会社が成長基調にあることを示すものは、そのKPIとなる数値が”Up and to the right(右上がりに伸びている)”ことにつきるからだ。
また、KPIに対してKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)という概念がある。これはビジネスの最終目標を定量的に評価できる指標として用いられ、「売上高50億円」といった収益目標や成長目標で表されることが多い。そのためKGIを達成するための過程をKPIを通して把握するといった関係性で用いられる。そして、プロダクトの最終目標となるKGIを、達成するための要素となるKPIに分解したものをKPIツリーと呼ぶ。
またKPIを策定するにあたって、気をつけなければならないことがある。KPIには2つのタイプがあり、どちらを目標としているかによってプロダクトマネージャーがやることが大きく変わってしまうからだ。
その2つとは遅行指標(Lagging indicator)と先行指標(Leading indicator)である。遅行指標とは、なにか投入努力の結果として表れてくるもので、例えば今期10億円の売上を達成したいというスタートアップの場合、この10億円は遅行指標になる。なぜならこの10億円の売上達成は、社内のさまざまな部署の努力(マーケティングによる認知度向上、プロダクト施策による継続率改善、営業サイドによる新規ユーザー獲得率の向上など)があって初めて実現できるからだ。
逆に先行指標とは、遅行指標につながる、先に現れてくる数字のことを示す。プロダクト施策で継続率が改善すればその「結果として」収益が上がるであろう。新規ユーザー獲得率の向上にも同じことが言える。その意味でこれら継続率や新規ユーザー獲得率は収益の前に現れる数字ということで先行指標となる。
効果的なKPIを策定する
一般的なKGI/KPIの考え方の問題点
ビジネスの成功を測定する意味でKGI/KPIという指標を使うことが効果的なのは、多くのビジネス書の指摘するとおりである。しかしこれまでの連載で述べてきたとおりプロダクトと事業が密接不可分になった今、従来のKGI/KPIでプロダクトの成功を測定することが必ずしも望ましいとは限らなくなっているのだ。
例えば、とあるB2CアプリのKGIを「売上高10億円」と収益目標に置いたとしよう。この時企業に何が起こるかというと、仮に売上高を上げるためにそもそもユーザーを増やさないといけないと考えてしまった場合、派手なTVCMを打ったり、広告をあちこちに展開することでインストールを誘発するきっかけをたくさん作り、ユーザー獲得に走ることになる。だがプロダクトが事業である以上、ユーザーがそのプロダクトを使い続けたり、有料ユーザーになるなどしなければ、売上をあげるどころか事業として成り立たなくなってしまう。プロダクトを通して企業が実現したい目標(収益や成長目標)をKGIとするならば、そのためにプロダクトで実現しなければならない価値が、継続的に生み出されユーザーに届いていることを別途計測する必要があるのだ。
従来のKGIという視点のみならず、プロダクトに特化したKGIを立てる必要があるのはこのためだ。これが次項で説明するNorth Star Metric(NSM)である。
North Star Metric
North Starの直接の意味は「北極星」であるが、「人々を迷うことなく同じ方向へと導くための光り輝く目標」という比喩表現でも使われる。これをKGIの考え方と組み合わせたのがNorth Star Metric(NSM)だ。
すでに多くのシリコンバレー企業で導入されており、NSMの定義は「プロダクトのコアとなる価値がユーザーに届いているかを知る、単一の指標」と言える。言い換えればスタートアップ企業、新規事業が長期的に成長しているかどうかを図る、経営・プロダクト両面で重要な指標なのだ。プロダクト面からすればどの方向にプロダクトをもっと進化させればよいかのヒントとなり、経営面からすればこのままこのプロダクトに投資し続けるべきかといったリソース的な判断の根拠としても使われる。
よいNSMとして大事なポイントには、以下の5つがある。
- NSMの改善がユーザー体験の向上とリンクしている
- ユーザーがプロダクトにどのくらい定着しているかを示す
- NSMを目指すことでx軸に時間、y軸に収益や成長目標を取ったグラフが長期的には右上方向に進む
- 収益に結びつくための先行指標である
- 組織内で理解してもらいやすい
これだけだとイメージがわかないと思うので例を挙げてみよう。
例えばビデオ会議SaaSプロダクトのZoomだ。Zoomは執筆時時点で、2021年の会計年度での売上高1800億円を収益KGIにかがけている(参考)。そのためのNSMとして「Zoomで主催された1週間あたりのミーティングの数」を置いている。Zoomのプロダクトの価値はシンプルなビデオ会議の始めやすさや使いやすさ、画像・音声品質の高さにあり、その価値は会議の主催者だけでなく、参加者側でも感じることができる。両者がZoomでの良質なプロダクト体験を経ることで、参加者だった人が主催する会議でもZoomを選択し、ひいては有料ユーザー化や企業導入へとつながっていく。
このZoomのNSMを噛み砕いてみると、以下のようにまとめることができる。
| よいNSMのためのポイント |
ZoomのNSM: Zoomで主催された1週間あたりのミーティングの数 |
|---|---|
| NSMの改善がユーザー体験の向上とリンクしている | 音声画像が高品質なビデオ会議をどこよりも簡単に実施できる |
| ユーザーがプロダクトにどのくらい定着しているかを示す | 1週間あたりのミーティング数は新規ユーザーや既存ユーザーが増えるに従って大きく増える |
| NSMを通して実現する成長指標のグラフが右上方向 | 収益KGIを達成するためには有料ユーザーが増えなければならず、1週間あたりのミーティング数が増え続けると、有料ユーザー数も増えることにつながる |
| 収益に結びつくための先行指標 | 1週間あたりのミーティング数が増えないことにはそもそも収益も増えない |
| 組織内で理解してもらいやすい | どのようなバックグラウンドの人でもわかりやすい |
従ってこのZoomのNSMは上記の5点を全て満たしていると言えよう。「収益が上がる」という遅行指標を実現するための先行指標がNSMであることがご理解いただけたと思う。
一つ注意したいのが、NSMは数字の操作が簡単であってはならないということだ。「10億円の売上さえ立てればプロダクトは成功」といったように収益目標をNSMとしてしまうと、先行指標となるプロダクトのユーザー体験の改善はおざなりになり、数字を達成するためにはなんでもやることになってしまう。そうすると結果的にユーザー体験の改善が後回しになったり、不用意に大きな案件に飛びつくことが優先となってしまう。
また、先の例のようにアプリのダウンロード数をNSMとしてしまった場合、ダウンロード数は多大な広告費を投入することで増やすことは可能である。こうするとプロダクトそのものがよくなっていないのに、プロダクトが成長していると勘違いしてしまうのだ。長期的にはその姿勢がプロダクトの命取りともなるので、従来のKGIとNSMは区別して使う注意が必要だ。
収益目標や成長目標としてのKGIを設定することは必要だが、プロダクトに特化したKGIとしてのNSMとの連携があって初めて実現されるという点は、プロダクトマネージャーとして理解しておこう。
NSMを達成するための主要因
NSMが無事設定されても、それで終わりではない。次にプロダクトマネージャーとして考えなければならないのは、「どうすればNSMを増やすことができるのか」である。
NSMを利用する場合には、NSMを上げる主要因は何か、といった論理分解をするのである。先のZoomの例を使うと、「Zoomで主催された1週間あたりのミーティング数」を増やすためには、ユーザーが使いたくなるような機能が豊富、ユーザーがさまざまなミーティングシーンで使ってくれる、ユーザーが繰り返し使ってくれる、会議の主催者と参加者がストレスなく会議を行える、といった要素に分解できる。こうした要素がもれなくダブりなく達成できて、ようやくKPIへの落とし込みが開始できるのだ。
また、KPIへの落とし込みがうまくいかない、あるいは辻褄が合わないのならば、切り口を変えるなどして達成要因の導き方を変えてみよう。この往復作業がNSM向上の実現に向けてのKPIを研ぎ澄ませてくれるはずだ。書籍では具体例を含めてKGI/NSM/KPIのツリーを紹介するので参考にしていただきたい。